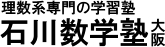十年ほど前のことでしょうか、愛車に不思議な偶然が続きました。
出張帰りが遅くなった早朝の国道24号、ウワナベ古墳付近を南進中、ドカン!という大きな音と、対向車線から中央分離帯を乗り越えて目前に転がるパッカー車、全身血だらけの男が這い出してきました。
どうやら中央分離帯の切れ目からUターンしようとしていた収集車に、トラックが追突したようでした。平和な月曜の朝が、一瞬にして地獄絵図になった瞬間です。
この十日後くらい、残業明け午前4時頃の阪奈道路を東進中、秋篠川を越えたあたり、ハザードをつけて斜めに停まった車と、その横に無造作に転がった物体。
「何事?」と車を停めて見に行きますと、呆然と立ち尽くす若者(かなりアルコール臭あり)、ピクリとも動かない初老の男性、フロントガラスがメチャメチャの車、なるほど交通事故現場でした。おそらく飲酒+死亡事故です。
若者と話しても意味不明でしたので、警察と救急を呼んで現場を後にしましたが、まるで絵にかいたような酷い状況でした。
このほかにも、高円山から飛び出してきた鹿に、正面から突進されたり、まちがって獣道に迷い込んで泣きそうになったりと、携帯電話の発信履歴が、警察と消防とJAFだらけになっていき、なんぼ鈍感な私でも、「こりゃ、だめだ!」と気づいた次第です。
それから今日に至るまで、運転席に護符をぶら下げるようにしました。なんとも霊験あらたかなお札のようで、なるほど住民票やら車検証やら、ありったけコピーして持って行き、二時間余りも祈祷していただくだけのことはあると感じます。
私は「怪力乱神を語らず」、およそ神仏を信じるものではありませんが、人智を超えた存在を、あたまから否定するものでもありません。それはきっと、「神」と呼んで差支えないものなのでしょうから。