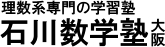「官僚的」という言葉があります。「通りいっぺんの」とか、「肩ひじ張った」とか、果ては「血の通わない」とか、何かとマイナスイメージに捉えられがちな言葉だそうです。
「官僚って、そもそも何?」という質問も、たくさんいただくようになりました。「どこにいるの?」、「何をしてるの?」、「誰のことなの?」…と。
小生の大学の同級生のMくんは、文部科学省にいて、文部科学行政を担っている官僚で、昔は気のいいオッサンだったんだけど、いったいどんな顔して「官僚」してるのかなぁ…とか、某国大使館にいるTくんも同級生だったんだけど、とにかくまじめで口が堅い奴で、外交秘密を扱うには天職なのかなぁ…とか、具体例を出せば出すほど、五里霧中に感じる皆さんもいらっしゃいます。
少し事情を知っっている皆さんは、「天下りする人たちだね。悪い人たちなの?」…などと。
昔も今も「官僚」するのは、楽じゃないのでしょうか。
一方で「官僚、大いに結構。仲間になろうじゃないか!」と、大声を張り上げた豪傑がいます。我が国の初代内閣総理大臣・伊藤博文公です。
博文伯爵がおっしゃるには、官僚の親分が政治家、政治家は選挙に落ちたらただの人、だから有権者の嗜好品になり下がることしばしば、親分のポピュリズムがこの国のあり様をコロコロ変えちゃ堪らない、それには官僚がしっかりすること、官僚がこの国をブレずに舵取りすればよい…と。
博文伯は、官僚養成機構としての帝国大学(当時は、のちの東京帝国大学のみ)を重視、文部行政の親分に、官僚を御するに慣れた開明派・森有礼子爵を起用したのでした。
帝国大学卒業の官僚たちが、のちの博文伯率いる政友会に流れ込み、名実ともにこの国を引っ張っていくことになるという歴史的事実、…多くの皆さんが知るところであります。
博文伯の先見に驚くとともに、ものごとを一面的に見るのではなく、多様な観点を持ち続けたいものだと、今も思い続けています。