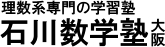大和田原(やまとたわら)と聞いて、「ああ、あのあたりね」と、すぐにうなずけるかたは、かなり少数派かもしれません。
宇治茶の産地「宇治田原」に比べ、いかにも影が薄いです。
車でしたら高円山の横からグ~ンと登っていきます。それほど時間がかかるものでもありません。
この大和田原に、一ヶ月に一度、二時間に一本しかない奈良交通のバスに乗って、通いつめた研究者がいました。
大正期から昭和初期にかけて、比較的裕福な農村で盛んに行われた青年団運動を調べるためです。
あたりまえのことですが、人は学校だけで教育されるわけではありません。むしろ学校通いは、長い人生の中で、特殊なほんの一時期の出来事かもしれません。
昔の豊かな農村では、まさにそのごとくに、義務教育期以降の社会教育が充実していました。青年団運動は、その典型でした。
研究者は「田原村の字○○の○○爺さんの話」とか、「同じく田原村の字○○の○○ばあさんの話」とか、たいへんマニアックな史料をたくさん集め、一風変わった論文を書いておりました。
変わってはいましたが、私は研究者の論文が大好きでした。こんな理由からです。
爺さんやばあさんが若者だったころ、学齢期が終わっても学びたいと思いました。お百姓さんや木こりさんになるためだけでなく、よりよく住みやすい村を造るには学ぶべきだと考えたようです。
青年団は入会地の管理を手伝ったり、祭りの準備をしたりもしましたが、酒を飲んでクダを巻くばかりでなく、いやそんなことはほとんどせず、あれこれと集まって一生懸命勉強していた、その実態が研究者の論文から知られました。
農村の若い人たちには、より良き明日への「想い」が満ちていたのです。「想い」が自ら学ぶ人々を造り出していたといってもいいかもしれません。
勉強が嫌がられたり、捨てられたりする現代社会や都会のありようと比べて、なんと真逆であることでしょうか。
本来勉強は、こうしたものであったのだと思います。